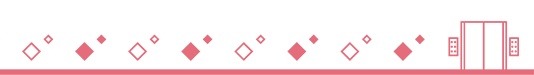chapter1.出会い
某高級ホテル。入口に立つベルボーイがにこやかに微笑み、「いらっしゃいませ」と私に声をかけてくれた。
中に入るとふんわりと香る柑橘系のフレグランスが、フロア全体を包んでいた。
レセプションで手続きをしている人、観光客やロビーのラウンジで寛いでいる人など、色々な人が入り乱れている。
私はそんな中をくぐり抜け、エレベーターホールへ向かう。
自分は金持ちでも何でもない、ただの社会人。けれど時々高級ホテルに来て、美味しい物を食べることが楽しみなのだ。
ホテルという空間には気分を高揚させる何かがある。今頭を下げてくれたホテルマンや、入口で微笑んでくれたベルボーイ達が、その夢の世界を作り出してくれていた。
この日は平日の昼間ということもあって、エレベーターホールには自分しかいない。空いていて良かったと思いながらエレベーターを待っていると、チン、とベルが鳴りエレベーターが到着した。
すると背後から男性の声が聞こえてきた。
「お待ちください」
追いかけてくる男は焦ったような声を出していた。
「うるさい、俺は行かないぞ」
二人はなにやら言い合いをしながらこちらに向かってくる。
(どうしたんだろう?)
気になりながらも、私は到着したエレベーターに乗り込んだ。
目的のカフェがある階を押し、扉が閉まる。
そのときだった。
「そのエレベーターは違いますよエリオット様」
「そのくらい分かっている! お前が追ってこなければいい話だ」
「それはできかねます」
「だからついてくるなと言っているだろう?」
エリオットと呼ばれた男性とそれを追ってきた日本人らしき男性が、エレベーターのドアが閉まる瞬間に飛び込んできた。
私のことが見えなかったのだろう、勢いよく体が当たり、少しよろけそうになったのをエリオットが支えてくれた。
そのとき、ふわりと香ったフレグランスがきつくもなくとても上品で、私はドキドキしてしまう。
「うわっ、何ということだ、女性に体当たりをしてしまうなんて……申し訳ない、勢いよく当たってしまった。お怪我はありませんでしたか?」
品の良い口調、キラキラとした髪、それにモデルのように整った容姿。まるで王子様みたいだと思った。
「お前も謝れ、笠原。お前のせいだぞ? 追いかけてなんて来るから」
叱咤する口調でエリオットが笠原に言う。その言い方は人に命令することに慣れている感じがした。
「申し訳ございません。私の主人があなた様に御迷惑をおかけ致しまして……」
笠原と呼ばれた男性は、綺麗な所作でお辞儀をして謝ってくる。
私が、特に迷惑だなんて思っていないと告げたその時だった。ガタンと大きな音を立てエレベーターが止まってしまった。
「ん? どうしたんだ? 故障か?」
ボタンを確認しながらエリオットが綺麗な顔を怪訝そうに歪める。
メインの電気も消え薄暗い状態の中、私も何事かと思い戸惑ってしまった。
「そのようですね。電気も消え非常灯になってしまったようですね。あなたは大丈夫ですか?」
笠原が、私のことも心配してくれて声をかけてくれた。
「もし、怖いようだったら私の手を握っているといい」
ご主人様らしきエリオットが、そう言って私に手を差し出してきたので、大丈夫ですと返したけれど、内心ではちょっと失敗したと思ってしまった。こんなにかっこいい男の人と手を繋ぐチャンスなんて早々ない。
「そうか……それならば、こういった方がいいかな? 私が怖いので手を繋いでてくれませんか?」
そう言ってエリオットがおどけてまた手を出してくる。私を不安にさせないために気を遣ってくれているのだろう。薄暗い中でも彼のほほえみは輝いてみえた。
「またあなたは……そういうことを軽々しく……」
すると笠原が呆れ声を出してエリオットの手を叩き落とした。
「いって」
なにするんだ、とエリオットは自分の手を撫でる。
「大変失礼いたしました」
笠原が私に謝罪してくれたけれど、私はむしろ嬉しかった。
すると私の心を読んだように、今度は笠原が恭しく手を指し出してきた。
「不肖の主人に代わりまして私があなたのお手を……」
パシ、と音がするとエリオットがさっきのお返しだと言わんばかりに、笠原の手をたたき落とした。そのやりとりが気の置けない感じがして楽しい二人だと思った。
思わず笑いが漏れると、エリオットがしてやったりという顔で笠原に言う。
「痛いですよ、エリオット様」
「ほら、お嬢さんに笑われしまったじゃないか」
「私は緊張を解そうとしただけですよ」
「っていうか、お前が暗いところ苦手なだけだろ?」
図星を指されたのか、エリオットの言葉に笠原が狼狽えた。
「う、うるさいですよエリオット様」
そんな笠原にエリオットが手を差し出した。
「しょうがないな~。お前の手は俺が繋いでてやろう。ありがたいと思え」
エリオットはそう言って勝手に笠原の手を取って繋ぐ。
「何が悲しくて男同士で手を繋がなきゃ行けないんですか……」
呆れた様子で笠原が手を振り払った。嫌そうにしているけれど、それもポーズなのが分かり、そんな二人を私はなんだかほほえましく思った。
「嬉しいくせに、照れるな」
すげない態度を取る笠原にエリオットが肩をすくめて私に教えてくれた。
「ちぇ。昔はもっと純情で可愛かったんだよ、こいつも」
「まったく……余計なこと言わないでください」
笠原が溜息を吐いたその時、緊急連絡用のスピーカーから連絡が入った。
笠原がスピーカーのボタンを押すと声が聞こえてきた。
『大変申し訳ありません。電気系統のトラブルでエレベーターが停止してしまいました。今業者がこちらに向かっております。少しの間お待ちください。ご気分は悪くありませんか?』
管理会社の担当者の声が聞こえてくる。
「ここには男性二人、女性一人が閉じ込められている。なるべく早く対処を頼む」
エリオットの声は毅然としていて、とても格好良くて思わずドキドキしてしまう。
「このあとお約束している先方に連絡を入れておいたほうが良さそうですね」
復旧まで時間がかかりそうだと判断した笠原が、携帯を取り出しどこかに連絡を入れていた。
「俺としては、これで行かずに済む口実ができたのでありがたいがな」
「まったく……」
したり顔のエリオットに、笠原が大きく溜息をついた。そのやりとりを見ていた私に笠原が気づいた。
「ああ、すみません。私たちだけで会話してしまって。ちょっと会食で人と会うはずだったですが、この人が気乗りしないと逃げ回っていたんですよ。そうしたらこの有様で……私が溜息を吐くの分かって頂けますか?」
すると今度はエリオットが言い返してくる。
「だってひどいと思わないかい? ただの会食かと思いきや、相手は体(テイ)の良い見合いをさせようとしているんだよ。俺はまだ結婚には興味はないといっているのに」
とオーバーリアクション気味に溜息を吐く。
「しかたないじゃないですか。懇意にして頂いている日本の旧家のお嬢様なんですから、当家としても無下にはお断りできるわけないじゃないですか。あなたは笑っていればハンサムな王子なんですから、黙って座っていればそれだけでいいんですよ」
しれっと笠原はエリオットに対してひどいことを言う。そんな笠原に対してエリオットは少しむくれつつも、けれど怒っているわけではなさそうだった。
「黙ってって……お前な~……。ね? こいつひどいだろ? 俺の方がご主人様なんだけど、いつもこの物の言い様なんだ」
どうやらこのやり取りはいつものことらしい。
「あなたが私に苦労ばかりかけるからでしょうが」
そう言って笠原が肩をすくめた。私は気になったので二人の関係を聞いてみた。
すると笠原は少し考え込んだあと、答えてくれた。
「私は長年エリオット様の執事をさせていただいています。日本では執事喫茶などもあるらしいですね。けれど私は――本物ですよ、お嬢様」
そう耳元で囁かれドキドキしてしまった。笠原は艶っぽくてとてもいい声をしているのだ。
それを聞いていたエリオットが、会話に入ってきた。
「そんなことを言ったら、俺は本物の王子だぞ?」
反対の耳元で今度はエリオットが囁いてくる。両耳でささやかれて私は閉じ込められていることなんて、すっかり忘れてしまっていた。
「エリオット様! その件はご内密にと何度も」
焦る笠原に、エリオットは別にいいじゃないか、と平然としていた。
「このお嬢さんとは、こんなところに閉じ込められた縁だ。俺の素性を知ってもきっと内緒にしてくれるさ。そうだろ?」
金髪碧眼の王子様に、間近でそんなことを言われたら頷くことしかできない。
「黙っていてくれるか? ありがとう。あなたが良い人でよかった」
「ほんとに。この件はくれぐれもご内密に」
そう言った笠原が私にウインクをしてくるので、思わず顔が赤くなってしまった。
「お前、どさくさに紛れてウインクなんてしやがって……このたらしめ」
「なに言ってるんですか、そんな変な意味はありませんからね?」
そのやり取りに笑ってしまい、私が楽しい人たちですね、と言うと二人は少し驚いたような顔をした後、満足げな笑顔になった。
「楽しい人達と言われるのは……悪い気分ではないね。こんな閉じ込められた空間だ。少し、我々と話をしながら過ごしませんか?」
微笑んでエリオットが私にそう言ってくれる。
「それは気も紛れて良いかもしれないですね。このエレベーターが動くまでもうしばらくかかるということでしたから」
笠原の言葉に私が頷くと、エリオットは王子様然とした笑みで言った。
「お付き合いいただけますか、レディー?」
chapter2.ふたりの物語
「あなたもこのホテルに宿泊をしているんですか?」
そう聞かれ、私はこんな高級ホテルに泊まれるわけがないと、首を横に振って今日ここに来た理由を話した。
「このホテルのカフェを利用しに来たのか。ここのスコーンはとても美味しいので俺も好きだよ」
そうなのだ。とてもサクサクしていて、バターの風味もあってとても美味しいと私も思っていたので、エリオットがそう言ってくれたのが嬉しくて、私は思わずスマホの写真を見せた。
「スマホのアプリに食べ物の写真がいっぱいだ。このSNSは日本でも流行っているんですね。エリオット様はご存知でしたか?」
そう笠原に聞かれ、エリオットが少し顔を少ししかめる。どうやら彼はそういったソーシャルネットワークが苦手なようだ。
「聞いたことは、ある」
エリオットもアカウントがあるのか、聞いてみた。
「俺はSNS全般に疎いからやり方も知らないが、君と繋がれるなら、やってみるかな?」
そんなことを囁かれたら嬉しくなってしまう。しかもウインク付きだ。モテる人が言うと何でも格好良くなるんだなと感心してしまった。
「とかいって、エリオット様、どうせ三日坊主になるのだからおやめなさい」
性格をよく知っている笠原にそう言われ、エリオットは少しムッとした表情をする。
「ほんと、お前は人のことをなんだと思ってるんだ?」
「仕事以外はテキトーな人、ですかね?」
「そんなことはないぞ! 君なら分かってくれるよな?」
と笠原にそう言われ、エリオットは慌てて誤解だと言わんばかりに私の手を強く握ってくる。
けれど笠原は、エリオットのそんな必死ないいわけを一蹴した。
「分かるわけないじゃないですか。今、知り合った方にそんなこと言ったら、余計に疑わしいだけですよ」
その言葉にエリオットがフンと鼻を鳴らした。
そんなエリオットをなだめるように、私は彼が本当にSNSをはじめたら是非繋がりたいと言ってみた。
「それは嬉しいな。本当に始めたらぜひフォローしてくれ」
そう言って微笑まれると、顔が赤くなってしまう。本当に彼は人にどう見られるかを知っている人だと思った。
「こんな主人に気を遣ってくださってありがとうございます」
笠原が気を遣って私にそう言ってくれる。反対側でエリオットが笠原に不満そうな視線を向けていた。
「そんな子供みたいに睨まないで下さいよ、エリオット様」
二人は私を挟んで軽い口げんかのようなことばかりしているが、仲が悪いわけではないのでそれが楽しい。
「こいつのせいで、俺の性格がねじ曲がった気がするぞ」
そういえば、さっき笠原は長年仕えていると言っていたけれど、いつから一緒にいるのだろうか。
気になって聞いてみると、エリオットが指を顎にかけ思案顔をした。
「そういえば笠原はいつから俺の傍にいたっけ? もう二十年くらいになるか?」
エリオットがとぼけたように言うと、懐かしむような顔で笠原が答えてくれる。
「そうですね、あなたが三歳で、私が十歳、でしたでしょうか。まるで人形のように愛らしい姿で、私の名前をうまく呼べなくて、それはもう食べてしまいたいほどの愛らしさでした」
笠原は昔のエリオットを思い出し、懐かしむように言う。
「今も食べてしまいたいほど愛らしいだろ?」
エリオットが自信満々に言うと、笠原がその口をつねった。
「どの口が言いますかね? この口ですか?」
「にゃにをしゅる」
「あははっ! まったく、可愛らしいご主人様だ。おっと、これでは執事のイメージが壊れてしまいますね。大変申し訳ございません、ご主人様」
わざとらしい言い方に、私も一緒になって笑ってしまった。
「ほら、また彼女に笑われてしまったじゃないか」
いつもこんな気の置けない感じなんですか? と私は聞いた。だって二人は一応主従関係ということになる。それなのにむしろ友達のような感じがするのだ。
その私の問いにエリオットが答えてくれた。
「こいつが俺に気安いのは、俺が頼んだからなんだ。小さな頃から公務で自由がなくて友達もどこかよそよそしかった。だから笠原には俺と一生友達でいろって言ったんだ。二人の時は敬語もいらないってね」
「友達は命令してなるもんじゃないでしょ、ってその場で言い返しましたけどね」
「こりゃ一本取られたって思って、それからはこんな感じなんだ」
二人が仲良しなのはよく分かった。そのやりとりから、お互い心から信頼し合っているのも分かる。
「あ、もちろん、普段はちゃんとご主人様然とされていますよ。私も、恭しく、仕えさせて頂いております」
主人に頭を下げながら言う笠原に、エリオットは高貴な雰囲気を醸し出す。それを見て私は彼が本当に王子なのだと理解した。
「一生お前は俺の物だぞ、笠原」
エリオットの言葉は意味深で、少しドキドキした。見てはいけないものを見てしまった気がしたので私は急いで話題を変えた。
それにしても二人とも日本語がとても上手なので、笠原に教えてもらったのかと問うと、その通りだとエリオットが教えてくれた。
「日本語かい? そう、こいつが俺の日本語教師だ。笠原は憎たらしいくらい綺麗な顔して国籍不明だろ? 仏頂面をやめればもっとモテるのにな」
仏頂面はしていないと思うけれど、確かに彼はクールビューティという言葉が似合う。
「私は生粋の日本人家系ですよ。両親が海外へ移住し、執事としてエリオット様の母君のご実家にお仕えしてから生まれたので、日本国籍ではありませんが」
と教えてくれた。
「笠原の父親は、これがどこをとっても完璧な執事で。笠原の進化系みたいな人物だ」
そんなにすごい人なのか、と感心していると、少しむくれた笠原の声がした。
「父と比べられるのは、嫌いですよ」
「お前は、本当に父親がコンプレックスだな」
くすりとエリオットが笑った。それに対してまた少しむくれた表情を見せた。。
「あんな完璧な執事、他に居ませんからね……」
エリオットに対するものとは違う、感情的なものを感じ私は父親のことを嫌っているのかと思って聞いてみた。
すると彼はこほんと咳払いすると、少し恥ずかしそうにした。
「え? 父親のことを嫌いなのかって? 嫌いじゃなくて、尊敬していますよ。けれど超えられないから憧れて、嫉妬もするんです」
素直な彼の言葉に、そうか、そういう感情を口にしてもいいのかなと思い、自分が仕事で悩んでいることを話した。
すると笠原が私を慰めてくれた。
「……あなたも仕事で悩んでいることがおありですか? けれどあなたの働きはきっと周りの方が見ていて、ちゃんと分かってくれる人がいるはずです」
話を聞いていたエリオットが励ましてくれた。
「結果が伴うと、自信にもなる。報われないことなんてないはずだ。君はこんな私たちに付き合ってくれるコミュニケーション能力もある。きっとうまくいくはずだよ」
仕事は人それぞれ違うものだが、そう言ってもらえると元気が出た。
「その調子。まずは焦らず、肩の力を抜いて、いつもその可愛い笑顔を見せていれば周りも味方してくれる」
エリオットの笑みに、私も自然と笑顔になった。
「エリオット様の笑顔は、私がいうのもなんですが、確かにとても魅力的ですからね」
「お、やっと俺のことを認める気になったか?」
「いつもちゃんと認めてるじゃないですか」
エリオットはその言葉をあまり信じていないような視線を笠原へ向けていた。
そんな話をしているうちに、かなりの時間が経っていた。
けれど未だエレベーターは動いていない。
「それにしても、まだ復旧はしないのか?」
「ずいぶんと時間がかかってますね……あなたは誰かと待ち合わせをしていらっしゃったんですか?」
そう聞かれ、私は首を横に振る。誰かと一緒におしゃべりしながらも楽しいけれど、一人でき気楽に来るのも好きなのだ。
今日はその後者の方だった。
「え? 一人で?」
そう言われ頷いた。
「そういう楽しみ方も、俺は嫌いじゃない。恋人に合わせるだけが全てじゃないしな」
恋人がいれば、それはそれでまた楽しめたのかもしれないが、自分には今特定の人はいない。
そのことを話すと驚かれてしまった。
「恋人はいないって!? こんなに可愛いのに? 笠原もそう思わないか?」
「驚きですね。こんなに素敵な方に恋人がいないなんて……私が立候補したいくらいです」
二人の言葉はお世辞でも嬉しかった。
「ほう……笠原は、彼女のような人がタイプなのか」
「美人は好きですよ? おや、エリオット様、ヤキモチですか?」
そのヤキモチはどっちに? なんて思ってしまう。
しばらくの間、二人との会話が楽しくて閉じ込められていることを忘れてしまうほどだった。
突然バチンと大きな音がした。それと同時に、付いていた非常灯が消えて真っ暗になってしまう。
「うわっ、どうしたんだ? 電気も消えてしまったじゃないか。大丈夫か? さあ、俺の手を握っているといい」
エリオットが私の手を取って握った。
「エリオット様はそこから動かないで下さい。今私が……連絡、を……」
笠原の語尾に力がなくなっていった。どうしたのだろうと横を向くと笠原が少し汗をかいている。顔色は薄暗いのでよく分からないけれど、調子が悪そうだった。
「ああ……すみません……大丈夫です。情けないことに、少し、暗いところが苦手なんです……」
笠原は息も少し荒く、辛そうだった。
「大丈夫か? 笠原。ちょっと待ってろ」
エリオットが携帯のライトを点けるのを見て、私も自分の携帯を取りだして同じようにすると、かなり明るくなった。
「これでどうだ? 携帯のライトでもないよりマシだろ?」
「エリオット様……申し訳、ありません……」
「ったく、こんな時ばっかりしおらしくなりやがって」
心配していると、笠原の代わりにエリオットがお礼を言ってくれた。
「あなたも心配してくれてありがとう」
私は笠原が気になってしまい、どうしてこんな発作が出るのかを思わず聞いてしまった。
「これは……トラウマなんだ。俺が、作ってしまった」
今度はエリオットの声が辛そうになった。なにかとても後悔しているような、そんな感じだった。
そんなエリオットの言葉を笠原は否定する。
「違いますよ。エリオット様の、せいでは、ありません……」
笠原はエリオットをかばうけれど、エリオットはそれでも俺のせいだと言った。
「笠原は、俺の代わりに地下牢へ閉じ込められたんだ。我が家は代々続く城に住んでいるんだが、そこは古いだけあって、地下に罪人を閉じ込めておく牢屋があったんだ。俺の母は後妻でな。父上の先妻は兄上たちを産んだあと病気で亡くなって、母は兄上たちの世話係として娶られたようなものだった。なのに、しばらくして年の離れた私が生まれたことが、彼らは気に入らなかったようだ。物心が付いた頃からよくいじめられていたよ」
過去にあったことを、話してくれた。彼らも色々と苦労してきたんだなと思った。
だからこそ、こんな私にも優しくしてくれるのだろう。
「エリオット様は、奥様によく似ていらっしゃって、容姿もよろしくて、子供の頃はそれはもう愛らしく……旦那様も大層可愛がられていて……」
笠原は少し落ち着いてきたのか、口調もしっかりとし始めていた。
「そのせいで、風当たりも強く……私が、お守りするのだと、初めてお会いしたときから、心にそう誓って、おりました」
「兄上たちが、いつも私をかばう笠原に腹を立て、地下牢に閉じ込めてしまったんだ。今はこんなだけれど、その頃まだ十歳かそこらだった笠原には、真っ暗闇の古い檻の中で丸一日過ごす恐怖は……大きな傷になって当然だ」
私はその話を聞いて、そんな小さな子供になんてひどいことをするんだろうと、怒りがわいてきた。今こんなにステキな人たちだ。子供の頃も可愛かったに違いない。
「でも、あの事件が旦那様の耳に入ったおかげで兄君たちも大人しくなりましたし、私はエリオット様のお役に立てて、よかったと思っていますよ」
笠原はそう言って、まだ青い顔でそれでも笑った。
「俺は、あの時に誓った。兄上たちに負けぬ立派な主君になろうと。人の痛みを分からない人間には、人の上に立つ資格はない」
その声は、とても凜としていて、エリオットの覚悟が含まれていたような気がした。
幼い頃の彼らを慰めるつもりで、私は笠原の手を握った。
「……ああ、お嬢さんの手は、暖かいですね。ずいぶん昔のことですから、私は大丈夫ですよ。でも、慰めていただきありがとうございます」
「本当だ。君の手は、人を癒やしてくれる、柔らかく暖かい手だな」
そう言ってエリオットも私の手を取った。すると三人で手を繋いでいる形になった。
「エリオット様と、あなたのおかげでだいぶ落ち着きました。大変申し訳ありませんが、電気が復旧するまで携帯のライトをこのままにしておいてもよろしいですか?」
笠原の頼みに、エリオットの声はなんだか嬉しそうだった。
「他でもない、お前の頼みなら」
「あなたもありがとうございます。ここから出られた暁には、なにかお礼をさせて下さいね」
私へのお礼も忘れずに言ってくれる彼は、気の利く優しい人だ。
「またそうやって、彼女を口説こうとしているな?」
エリオットがわざとらしくそう笠原に言う。
「またそうやって、エリオット様はヤキモチをやく……」
おどけた笠原の言葉に、二人は顔を見合わせて、声を上げて笑って楽しそうにしていた。
chapter3.別れ
「それにしても、お互い災難だな。こんなところに閉じ込められるなんて」
けれどあなたたちと一緒だから、むしろ幸運だと伝えた。
「そんなふうに言ってくださるなんて、あなたはやっぱり優しい方ですね。それは私たちにも同じ気持ちですよ。あなたのような方とご一緒できるなんて、不幸中の幸いというのでしょう」
もう自分を立て直した笠原がにこやかにそう言ってくれるので、私も嬉しかった。
「そうだな、俺も君のことをもっと知りたいから、この扉が開くまで、もうしばらく付き合ってくれると嬉しい」
もちろん、と答え、私は彼らにどうして日本に来たのかと尋ねてみた。
「観光、と言いたいところだが、仕事だ。内密の案件で、自由に遊びにも行けない」
そう言ってエリオットが肩を竦める。
「こう見えても、エリオット様は意外と有能で多忙なのです」
「こう見えてとか意外とか、必要ないだろ。そのまま有能と言えば良いのに、お前は本当に俺のことをなんだと思ってるんだ」
ぶすくれるエリオットの手を取って笠原は笑う。
「大切な、ご主人様です」
この二人の関係は、私には計り知れない。なんとなく、あやしい雰囲気もするのだ。
すると非常灯がチカチカとして、エレベーターの照明が戻った。
「明かりが戻りましたね」
「おお、やっと戻って来たか。君とこうして話をしているのは楽しいけれど、さすがにそろそろ外の空気が吸いたくなってきたな」
その言葉に頷いて、私は大きく息を逃がす。なんとなく、目の前がくらくらする。狭い空間で少し気分が悪くなってしまったようだ。
「少し、顔色が悪いようだな。大丈夫か? 気分が悪いようなら私に寄りかかっているといい。私の母は、気分が悪いときは、こうしてよく背中を擦ってくれたんだ」
その思い出にやさしい母親だったというのが想像できた。それは彼自身、とてもやさしい人だからだ。
ありがとうございます、と私は少しだけ彼に寄りかからせてもらった。
「では、私は手を握っていましょう。安心して下さい。必ずここから連れ出して差し上げますから。さっき私を助けてくれたお礼をさせて下さい」
特にたいしたことはしていないのに、助けてくれる笠原はとても律儀で真面目な人だと思った。
「なにか楽しいことを、思い浮かべるのはどうだ?」
私の気を紛らわそうと、エリオットが話を考えてくれる。
「俺はこの仕事が終わったら絶対にバカンスを取る! そう決めているんだ」
「エリオット様。ちなみに、そんなバカンスの予定なんて入ってませんからね」
「取る! それを上手くやるのがお前の仕事だろ笠原! 俺は! 絶対に! 休む!!」
拳を握りしめるエリオットに、強いの決意を感じた。
「駄々っ子みたいなこと言わないで下さいよ……」
と呆れた声で笠原が言う。
彼らはそんなに忙しいかと、思わず心配になってしまった。
「ああ、ご心配には及びません。このところ確かにお忙しくてまとまったお休みをとれていないのです。まあ、それだけエリオット様が国民から人気ということなのですが」
笠原の話で、彼はとても国民から愛されているのだと知った。こんなに格好良くて優しい王子様がいるその国に住んでいる人たちは、きっと幸せだろう。
まだ明かりの付かないエレベーターの中で、笠原は具合の悪い私に気を遣って話を振ってくれた。
「あなたは、なにをしているときが一番楽しいですか?」
私は今日もこれからする予定だった食べ歩きのことを伝える。美味しいものは人を幸せにしてくれる。
「ああ、食べ歩きか! そういえば、今日もこのホテルのカフェを目当てに来たと言っていたもんな。笠原は? お前の楽しみは何だ?」
エリオットが笠原に話を振った。
「そうですね……そういえば、私はあまり自分の楽しみというのを考えたことがなかったかもしれません」
笠原の言葉にエリオットが不思議そうな顔をしていた。
「そうなのか? てっきり俺をいじめるのが楽しみなのかと……」
「ああ、それは間違いではありません」
「やっぱり……」
二人のやりとりに思わず笑ってしまうと、少し息が吐けた。
「ああ、よかった。少し笑顔になって下さって」
「ほんとだ。顔色も少し良くなったな」
二人に心配かけてしまい恐縮してしまう。
それより笠原の楽しみは、なんなのだろうか。エリオットも知らないようで、気になったので聞いてみた。
「私の楽しみですか?」
「俺も知りたいぞ」
「そうですね……きっと、先ほどエリオット様が仰っていたことが、正しいのかもしれません」
「俺をいじめることか?」
怪訝な顔のエリオットに、笠原は今までとは違う優しい笑みを浮かべていた。
「そうではなくて……私の全てはエリオット様に捧げたので……私の楽しみは、エリオット様に仕えることなのだと思います」
その笠原の顔は、本当に幸せそうで、見ているこちらが照れてしまうほどだった。
エリオットも少し照れている様子で、咳払いをして誤魔化していた。
「そ、それは楽しみとは、言わないだろ。こうもっと自分のためになにかしろ」
エリオットの言葉に、笠原はとても優しい顔で笑っていた。
「私はこれでいいのです」
そう言われたエリオットが、少し複雑そうな顔をしながらもとても嬉しそうだったので、私は思ったことを伝えた。
――笠原さんのことがとても好きなんですね、と。
「え、な、なにを言うんだい急に。俺が笠原のことを好きだなんてっ。もちろん、笠原のことは誰よりも信頼している。だから全てを預けられているというのはある。好きという、か……いや好きだけれども、これは情愛というか、なんというか……」
私が思ったままを口にしてしまうと、エリオットは急にしどろもどろになってしまった。そんなところも可愛らしい人なんだなと思えた。
「なにそんなに焦っているんですか。この方はそんな変な意味で仰ったわけでは無いと思いますよ。むしろ墓穴掘ってますよエリオット様。それに私はあなたのことが大好きですから」
笠原がふふっと笑いながらそう言った。
「う、うるさいっ」
エリオットの顔が真っ赤になっていた。
「ね、自分のご主人様なんですが、可愛くてついいじめてしまうんですよ」
とこっそり私に耳打ちしてきた。そんなに大切な人がいるなんて、と私はなんだかうらやましくなってしまった。
そんな話をしていると、がごん、とエレベーターが大きく揺れた。
電力が戻って、ウィーンという動力の音がする。
「お、やっと復旧したか」
「楽しいおしゃべりもここまでですね」
笠原が少し残念そうに言う。私も、もっと彼らとおしゃべりを楽しみたかったなんて思ってしまった。
「君と出会えてとてもよかった。だが、私のことはこの箱を出たら、知らなかったことにしてもらえると助かる。一応は正体を知られてはいけない身分だからな」
そう言ってウインクしてくるエリオットは、やはり格好良かった。
「この方なら大丈夫でしょう。信頼できる方だと思います。こんな狭い空間に、むさ苦しい男二人と閉じ込められてしまい、トラウマなどにならないとよいのですが……」
と笠原が心配してくれていたけれど、むしろいい想い出になった。
エレベーターが動き、移動を始める。
エリオットと笠原が二人でなにか話していた。
「あとあと面倒だから、俺たちと一緒にいるところを見られないほうがいいな」
エリオットの言葉に笠原も同意していた。
「扉が開いたら、外から見えないよう隠れていてください」
そう言って二人が盾になるように、私の前に立つ。
「さあ、現実へ、戻るぞ」
チン、と音がして扉が開いた。
「またいつか、この現実でもあなたと会えますように」
と笠原が恭しく頭を下げてから、私の手の甲に小さくキスを落とす。
エリオットが私の頬を撫でた。
「さようなら、可愛いお嬢さん」
そう言ってやさしく頬にキスをした。
エレベーターから出て行くエリオットの後ろ姿は毅然としていて、私の目には彼の頭上に王冠が見えた。
BL小説家。小説花丸より「永遠と一瞬」でデビュー。
現在はルチル文庫、電子書籍「小説花丸」で活躍中。
3月15日にルチル文庫より「束縛彼氏と愛の罠」が発売。その他作品「溺愛彼氏と小さな天使」「初恋のゆくえ」など、王道エンタメBL小説メインに執筆をおこなっている。